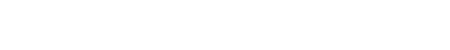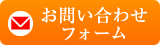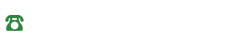申告期限はあっという間にやってきます
 相続が起きてから申告期限までの10か月はあっという間です。四十九日が過ぎたころから財産の洗い出しをはじめ、次に評価額の算出、遺産分割協議とやるべきことが次々と発生します。申告・納税が期日までに間に合わなければペナルティが課されます。そのため、相続が発生する前から準備をし万全を期すことが大切です。
相続が起きてから申告期限までの10か月はあっという間です。四十九日が過ぎたころから財産の洗い出しをはじめ、次に評価額の算出、遺産分割協議とやるべきことが次々と発生します。申告・納税が期日までに間に合わなければペナルティが課されます。そのため、相続が発生する前から準備をし万全を期すことが大切です。
また、事前から準備をすることは節税という面から考えた場合にも有用です。相続が発生してからではできることは限られます。生前に財産を贈与することで相続税を節税できることがあります。遺言書を作成し遺産分割を確定しておくことで相続税の節税や相続争いのを回避することもできます。このようなことから、当事務所では事前の相続対策をご提案しております。
ただし、相続が開始した後であっても、不動産(特に土地)の評価を最大限減額するためのノウハウもありますので、まずは気軽にご相談下さい。納税資金確保まで全力でサポート致します。
相続税申告のお手伝い
これまでは、相続があっても相続税がかかるのは100人中4人程度と言われておりました。そのため多くの方々が相続税に対してあまり関心を持っていなかったと思います。
今でも、「自分は資産家ではないから関係ない」と考えておられる方も多いのではないでしょうか?
しかし、下記のように相続税の基礎控除額が改正されたことで2015年1月からの相続では、自分には関係ないと思っていた方でも相続税がかかる可能性が出てきてしまったのです。
特に、地価の高い都市部に不動産をお持ちの方は要注意です。
【改正前】5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【改正後】3,000万円+( 600万円×法定相続人の数)
たとえば、相続人が3人だった場合、これまでは、基礎控除額は5,000万円+1,000万×3人=8,000万円でしたが、改正により3,000万円×600万円×3人=4,800万円になってしまったのです。
なお、基礎控除額とは、その金額までは相続税がかからないと考えていただくとわかりやすいかと思います。
相続があってからでは、被相続人の財産を贈与したり、不動産を購入して節税をするということはできません。しかし、土地の減額要素をみつけ評価額を下げることや、遺産分割を調整することで相続があってからでも相続税を軽減することはできます。
申告期限が近づけば近づくほどできることは少なくなります。(申告期限はお亡くなりになった日の翌日から10か月以内です。)
相続税はいくらかかるのか、そもそも何から始めたらいいのか、わからないことはすべてお答えいたしますのでお気軽にご相談ください。
初回のご面談の際に下記をご用意頂けるとお話がスムーズです
- お亡くなりになった方の家族構成(メモ書きで結構です)
- 現金や預金の概算(メモ書きで結構です)
- 固定資産税の課税明細書
主なサポート内容
- 財産・債務の調査・確定
- 財産・債務の評価、財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成、提出
- 納税資金対策
- 名義変更手続き(司法書士の斡旋を含む)
- 税務調査の立会い
相続税申告後のお手伝い
相続税の申告によりひとまず手続きは終了いたしますが、それですべて終りではありません。税務調査があった場合には調査の立会い、二次相続・三次相続対策のご相談もお受けいたします。
税務調査対応
もしかすると、申告後3年以内に税務調査があるかもしれません。
税務調査は、申告した税金が正しく計算されているのか、財産に漏れは無いかなどを主に調査します。
現在でも税務調査があることは2割程度ですので、基礎控除額が下がり多くの方々が相続税の申告をするようになれば、その割合はさらに下がると予想されます。
例え税務調査があったとしても、当初の申告が適正であることは勿論なこと、代理人としてしっかりと立ち合いも致しますので安心して調査に臨んでもらえればと思います。
相続財産の処分
相続が発生してから納税までの期間が10ヶ月しかありませんので、相続財産を処分して納税資金を確保するのは時間との勝負になります。この間に相続人間で遺産分割も行わなければなりません。
すこしでも早く処分をして納税資金を確保したいと考える相続人と、少しでも安く購入したいという買い手の利害を一致させる一番の方法は安値で処分するということになります。
しかし、それではお亡くなりになった方が大事にしてきた財産を相続税の納税のために安価で手放すことになってしまい思いを無駄にする結果となってしまうかもしれません。
そこで、とりあえずの納税資金の確保として金融機関との交渉をお手伝いすることや、本来の適正価格で財産の処分ができるよう信頼のできる業者をご紹介することもしております。
二次相続・三次相続対策
相続の手続きも終わり、相続税の納税まで済ませるとホッとしてしまうところですが、一次相続を経験することで事前にこうしていたら良かったという事も見えてきます。
次の相続まではまだまだ先かもしれませんが、一次相続を経験したことにより、事前にできることを考えるきっかけにもなると思います。長い時間をかけて何ができるかを一緒に考えていきたいと思います。
生前対策をお考えの方
一般的に相続は、ご先祖様から受け継いだ財産とご自分(及びその家族)で形成した財産を子孫に引き継ぐものと考えがちですが、財産だけでなく、家訓など目に見えないものも含めて、引き継いでいくものです。
相続税の問題だけ考えた対策をすると、残された財産を巡って家族が争いになり、場合によっては絶縁という事になることも少なくない話ですので、大切な家族がご自分が亡くなった後も仲の良い家族でいられるような生前対策をご提供いたします。
当事務所では、お客様のお気持ちをじっくりとお聞きし、お客様の希望する着地点を目指した相続対策をご提案いたします。
まずは財産をしっかり把握しましょう
とにかく円満に財産を分割し、相続後も家族が仲良く暮らすためには、家族構成やご家族の皆様それぞれの性格をお聞きすることから始めます。そして次に財産のことをお聞きします。
現実的なお話をすると「誰がお墓を守っていくのか」という事で相続後にもめるといった例は皆無です。もめる原因はやはり財産の分割になります。
そのため、家族のお話の後にはしっかりと現在の財産を確認させていただき、ご相談者にもしっかりと把握していただきます。
財産の構成とその総額がわかれば、相続後に支払わなければならない相続税額がある程度予想できます。まずは、何も対策をしなくても相続税の支払いに必要な資金があるのかを把握し、そこから相続税の対策と遺産分割の対策の両方をバランスよく考えます。
節税対策
相続税の節税対策は簡単です。
財産を使ってしまえば良いのです。しかし、「相続までに、すべて使ってしまってください。」と言っても使い切れるわけではないです。ご自宅を売却してしまえば住むところが無くなってしまいますし、何歳で相続をむかえるか決まっているわけではありませんので使い切るにも勇気がいります。
そこで、主として「生前贈与」と「財産の評価額を下げる」という2つの方法を使います。
ただし、ドラスティックな対策をご提案することもできますので、ご興味がある方はご相談ください。
①生前贈与
「生前贈与」とは、名前のとおり生前から相続人に財産を贈与し、総財産を減らすことです。
年110万円までの贈与は、贈与税がかからないことから110万円までの範囲において毎年贈与を行うことにより総財産が減少します。事前に相続税の試算をすることで相続税率が把握できますので、相続税の税率以下で贈与ができるのであれば贈与税を支払ってでも生前贈与を行うことも考えられます。相続がまだまだ先ということであれば長い年月をかけて財産を減らしていくことができます。
②財産の評価額を下げる
一般的に相続財産の評価は、財産評価基本通達をもとに評価します。
土地の評価一つをとっても財産評価基本通達にはさまざまなパターンがありますので、土地をどの状態にしておくことが評価額を下げる原因になるのかがわかります。ただし、財産評価基本通達どおりにすれば評価が下がるという事だけを考えてしまうと本当に実際の土地の評価を下げてしまうこともあります。
安易に相続税を下げることをせずに相続税の評価を下げることより大切なことを一緒に考えましょう。